学校案内の資料請求する♪

学校案内のパンフレットをみなさまに無料でお送りしております。
また、電話相談・オンライン相談・学校見学なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
学校案内の資料請求する♪

学校案内のパンフレットをみなさまに無料でお送りしております。
また、電話相談・オンライン相談・学校見学なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪

青楓館高等学院0期生のユキハです。
この記事では、不登校の原因がわからないときの改善策について、小中高と不登校経験のある私の体験談を織り交ぜてお話しします。
この記事でわかること
 ユキハ
ユキハ変わりたいと思ってこの記事を読もうとしてくれているあなたへ、何かしらのヒントになれば幸いです。


文部科学省が実施した不登校児童生徒の実態調査によると、最初に行きづらいと感じ始めたきっかけが「自分でもよくわからない」という人は、小学生で25.5%、中学生で22.9%を占めています。この結果からわかるように、不登校の原因がわからないのは珍しいことではありません。
不登校の理由は人それぞれで、見つけるのはとても難易度の高いことです。自分のペースでゆっくり探していけば、いつか納得のいく答えを見つけられる日が来ます。
まずは、一般的に挙げられる不登校の原因に当てはまるものがあるか探してみましょう。不登校の原因を見つけるための第一歩です。


具体的には、次のような状況で不登校になります。
校則に納得のできないもの・理由を聞いても理屈の通った説明をしてもらえないものがあると、不満が募って不登校になります。ブラック校則としてここ数年で度々耳にするようになりましたね。
校則以外にも、学校の伝統や暗黙のルールが合わないという場合も含みます。



私の中学校では、文武両道をアピールするために全員部活動に所属しなければならないというルールがありました。
勉強が理由で不登校になるのは、主に以下の3つの状況が考えられます。
嫌がらせを受ける、無視されるといったいじめによって居場所を失うことで、心身が傷つき不登校になります。
いじめとまではいかないような、ちょっとしたすれ違いが理由で不登校になることもあります。
明確な理由がないのになぜか気まずくなってしまうという場合も含みます。
先生と性格が合わない、信頼できないという状況も不登校の原因になり得ます。
運要素が含まれる上に最低でも1年は変わらないため、終わりが見えず耐えられなくなってしまいます。苦手な環境にいるときの1年はとても長く感じるものです。
特定の教科の授業が苦手であったり、マラソン大会などのイベントごとが苦手で行きたくなくなるという場合もあります。
このように、楽しく活動できる状態ではない場合、活動だけでなく学校自体に行く気が失せてしまいます。
このような気質を持っていたり、集団生活をしているときにトラウマになるほどの出来事を経験していたりすると、集団生活が基本である学校が苦手になりやすいです。
将来やりたいことが見つけられないのも、不登校の原因のひとつです。
このような理由から不安が増大し、体が動かなくなってしまいます。



学年が上がるにつれて、責任が重くなるので不登校の原因になりやすいです。


家族の仲が悪いのも不登校の原因になります。ピリピリした空気を感じ取って落ち込んだり、家での居場所を失って休息が十分にできなくなることで、学校に行く気力がなくなります。
このような急激な環境の変化があると、適応するために大きなストレスがかかります。
生活が困窮しているのも不登校の原因になります。家庭全体が重い空気になっているのに加え、教育費が出せない、子供も働いてお金を稼がないといけないということもあるのです。
子供が親に依存していたり、親が子供に依存しているというのも不登校の原因です。学校に行くと離れなければいけないので、「親がいないときに何か起きたらどうしよう」という不安から学校に行けなくなることがあります。
重労働により身体が疲弊する上に、誰かに相談することも力を貸してもらうこともできない場合が多く、心も疲弊します。心身ともに疲れている状態では、学校に通うことが難しくなります。
何らかの理由で生活習慣が乱れていると、朝起きて学校に行くことを負担に感じやすいです。不規則な生活習慣になるのは、以下のような理由が挙げられます。



生活習慣が乱れるのには様々な原因があります。単なる怠けだと断定するのは避けましょう。
家や学校に居場所がなく外に出ていた結果、非行に走って不登校になるケースもあります。先に紹介した家庭環境が影響している場合も多いです。
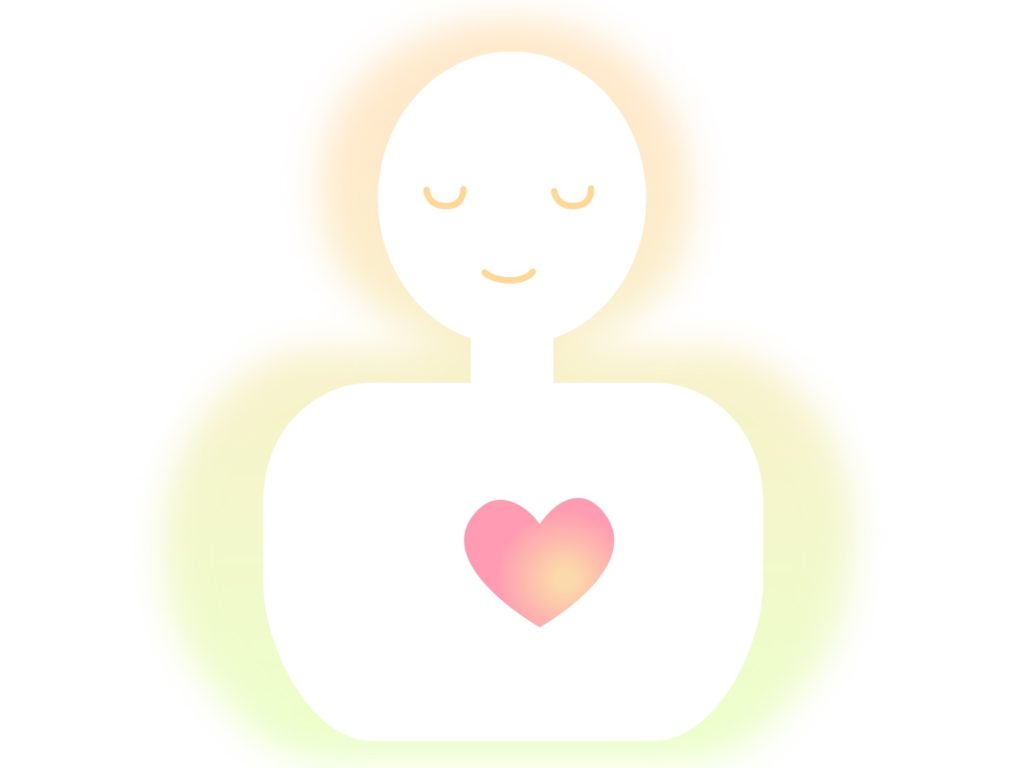
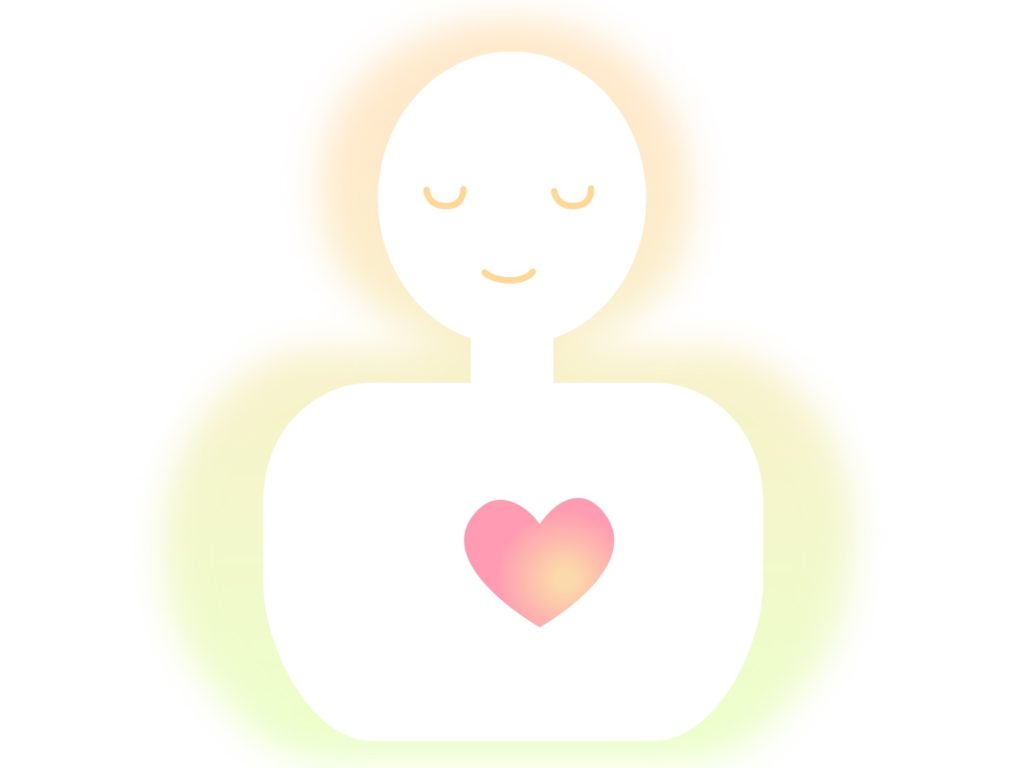
学校に意義を見いだせていない状態では、通おうと思っていても体が動かなくなってしまいます。環境の変化についていけなくなったときにも無気力状態になることがあります。
頑張りすぎることでも無気力や不安は起こります。部活や受験勉強などに打ち込んでいた反動で疲れがどっと来て無気力になったり、「これでよかったのかな…」と急に不安になったりします。
病気やケガで入院しておりしばらく学校に行っていなかった結果、行かないことに慣れたり行く意味が分からなくなることがあります。
鬱病や神経症を患っている場合も、学校に通うことが大きなストレスになります。
ADHD (注意欠陥多動症) やASD (自閉スペクトラム症) 、LD (学習障害) などの発達障害で不登校になることもあります。グレーゾーンの場合も含みます。
学校の仕組みが合わない、クラスメイトや先生と上手くコミュニケーションを取れないという状況で強い緊張や疲労を感じて不登校になります。
低血圧により朝起きるのが苦手でよく遅刻してしまい、学校が嫌になるという場合もあります。
また、学校の仕組みなどが元々合わない体質という可能性も考えられます。
例えばHSPと呼ばれる刺激に敏感な人は、学校を苦痛な場所として認識しやすいです。多くの人がいて多くの物があるという刺激の多い空間に一日中いなければならないとなると、疲れがどんどん蓄積されていきます。


不登校の原因はひとつとは限りません。原因がいくつも絡まっていたり、大きな原因がありながらも引き金となったのは小さな原因という場合は、特に見つけるのが困難です。
「この原因に当てはまってはいるけれど、なんとなく違う気がする」のであれば、別の原因にも目を向けてみましょう。
当初の悩みはなくなったけれど不安が消えないというときは、不登校が続くうちに原因が変わった可能性があります。
「学校に戻るのは周りからいろいろと言われないか心配だからできない」といった理由になる、などですね。
先に挙げた不登校の原因を確認し、それぞれが自分に当てはまるかどうか「○・△・×」で振り分けてみましょう。どんな原因が当てはまるのかを記号で明確に認識することで、本当の原因を見つけやすくなります。



もっと深く考えられそうであれば、当てはまる度合いを「%」で表してみるのも良いですね。
自分がリラックスできる場所や楽しく学校に通えていた時期と今の学校の違いを思いつくだけ書き出してみて、「この違いはなんとも思わない」「この違いは耐えられるレベルのもの」「この違いはものすごく大きくて耐えられない」の3つに分類してみると、答えに近づくことができるかもしれません。
自分の頭だけで考えると疲れやすいので、紙に書いてアウトプットすることで、もやもやを吐き出して整理することができます。整理できると、自然と考えが浮かんできます。
今してくださっているようにインターネットでもう少し情報を集めてみたり、一緒にいて安心できる人と話しながら考えてみると、自分では思いつかなかった考えに出会えることがあります。
不登校でもいいということを、まずは自分自身で認めてあげてください。「学校には絶対に行かなければいけない」「不登校の自分はダメなんだ」という考えでずっといると、疲れている心を余計に苦しめてしまいます。自分で自分の味方になってあげることが大切です。



いきなり認めるのは難しいので、最初は自分が「不登校はよくない」と思っていることを認識するというだけでも十分です。
ふとしたきっかけで原因を見つけられることもあるので、原因探しだけに目を向ける必要はありません。
また、原因を見つけられなくても改善できる場合はあります。考えすぎると疲れてしまうので、原因探しは気力が残っているときのみにしておきましょう。
不登校が解決したと言えるのは学校に通えるようになったときではありません。自分らしい生き方をしようと思えるようになったときです。
「学校に通うのは向いていない気がする」という場合は無理して通おうとせず、別の道にも目を向けてみてくださいね。


原因がわからない場合は改善の兆しが見えづらいので、
原因がわからないことによって本来の原因とは別の不安を感じてしまうこともあります。
原因がわからないと、当然ながら改善のために動き出すことが難しくなります。その結果良くなる兆しが見えずに不安な状態が続きます。
「不登校の自分はダメなんだ」という気持ちに「理由がわからないから甘えなんだ」「理由すらわからない自分は本当にダメだ」という気持ちが加わって、下がっていた自己肯定感が更に下がります。
家族からの「学校に復帰してほしい」という空気を感じたり、近所の人や学校の先生・生徒から変な目で見られていないか気になったりすることで、「どうしよう」「早く原因を見つけて解決しなければ」と焦って不安になります。



家族と会わないように気をつけていたり、外に出ること、特に平日の昼間に外に出ることが怖い場合は、周囲の目線がものすごく気になっている状態かもしれません。
不登校で勉強ができない状態が続けば続くほど、勉強がわからなくなってしまうことによる不安は大きくなります。
停滞している状態が続くと、将来もこのままなのではという不安が大きく膨れ上がります。原因がわかっている不登校よりも将来への不安は深刻です。


原因がわかっていてもわかっていなくても、こうして不登校について調べているということは、「現状を打破したい」「変わりたい」と思っている証拠です。ここでは、変わるためにできる具体的な方法をお伝えします。
しかし、変わるためにはたくさんのエネルギーが必要です。まずは十分すぎるくらい頑張った心を休めることに専念しましょう。「今なら大丈夫」と思えるようになったら実践してみてくださいね。
また、いきなり完璧に実践するのは難しいです。できる限りハードルを下げて、少しずつ進めていくことを意識してください。
原因が多種多様であるように、悩みを減らすための方法も人それぞれです。アレンジしながら自分に当てはめ、合う方法を探してみましょう。
ここでは学校に通いつつ試すことができる方法をお伝えします。
学校に行こうとするとお腹が痛くなる、涙が出る、体が動かなくなるという場合は、後ほど紹介する学校外でもできる方法を試してみてください。
学校で自分が安心できる居場所を見つけるのは比較的実践しやすい方法です。教室の隅や中庭、図書室など、休み時間になったらすぐに行ける場所を探してみましょう。



私の場合は人のいない場所が良かったので、ベランダや外階段、別棟の廊下の隅にある椅子が置いてあったスペースで休み時間を過ごしていました。
安心できる行動を取り、不安を忘れられるようにするのも良いですね。読書で本の世界に入ったり、音楽を聞いたりすることで、不安な気持ちを少しの間だけでも忘れることができます。
担任の先生だけでなく、保健の先生や部活動の顧問の先生など、親身になって聞いてくれそうな先生に話してみましょう。
ここからの改善策を実践するためには学校と相談する必要があります。また、周りから “普通とは違う人扱い” されるのが苦手な人にはあまりオススメできません。
登校頻度を週2回にする、午後だけ行く、特定の教科だけ授業を受ける、部活動のみ出るといった一部の時間のみ学校に行く方法です。長時間学校にいる必要がないため、終わりが見えやすく、少し学校に行くハードルが下がります。
原因が明らかに教室にある場合、別室登校をするのもひとつの手です。保健室や相談室、空き教室で過ごすことで、「学校」という場所への恐怖心を徐々に減らすことができます。
クラスメイトの特定の誰かや先生、クラスの雰囲気が合わないという場合はクラスを変えてもらうことも視野に入れてみてください。ただしクラスを変えることが可能か不可能かは、学校によって変わります。検討する場合はまず先生に確認してみる必要があります。
今の学校がどうしても合わない場合は、学校を変えるのもひとつの方法です。小学校から中学校へ上がるタイミングで少し遠くの学校に行ったり、中学校から高校へ上がるタイミングで通信制高校に行くなど、環境をガラッと変えることでまた通えるようになることもあります。
すぐに環境を変えたいのであれば、転校するということも可能です。ただし、書類の準備をしなければならなかったり、引っ越さずに転校したい場合は明確な理由が必要になったりします。難易度が上がるので、よく考えてから行動しなければなりません。



私は中学生の時に転校を経験しています。出席数が足りないと中学卒業資格を貰えない中高一貫校だったため、在籍校を一貫ではない中学校に変更しました。
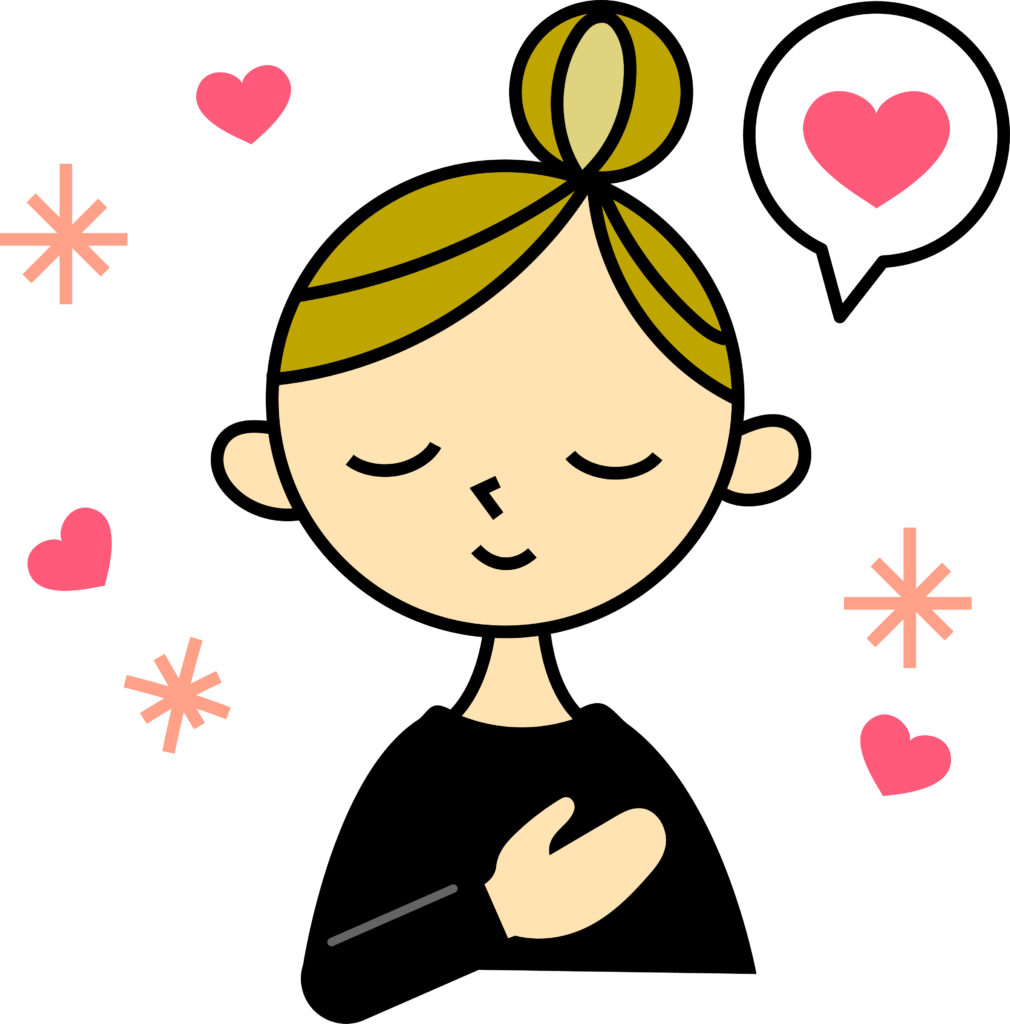
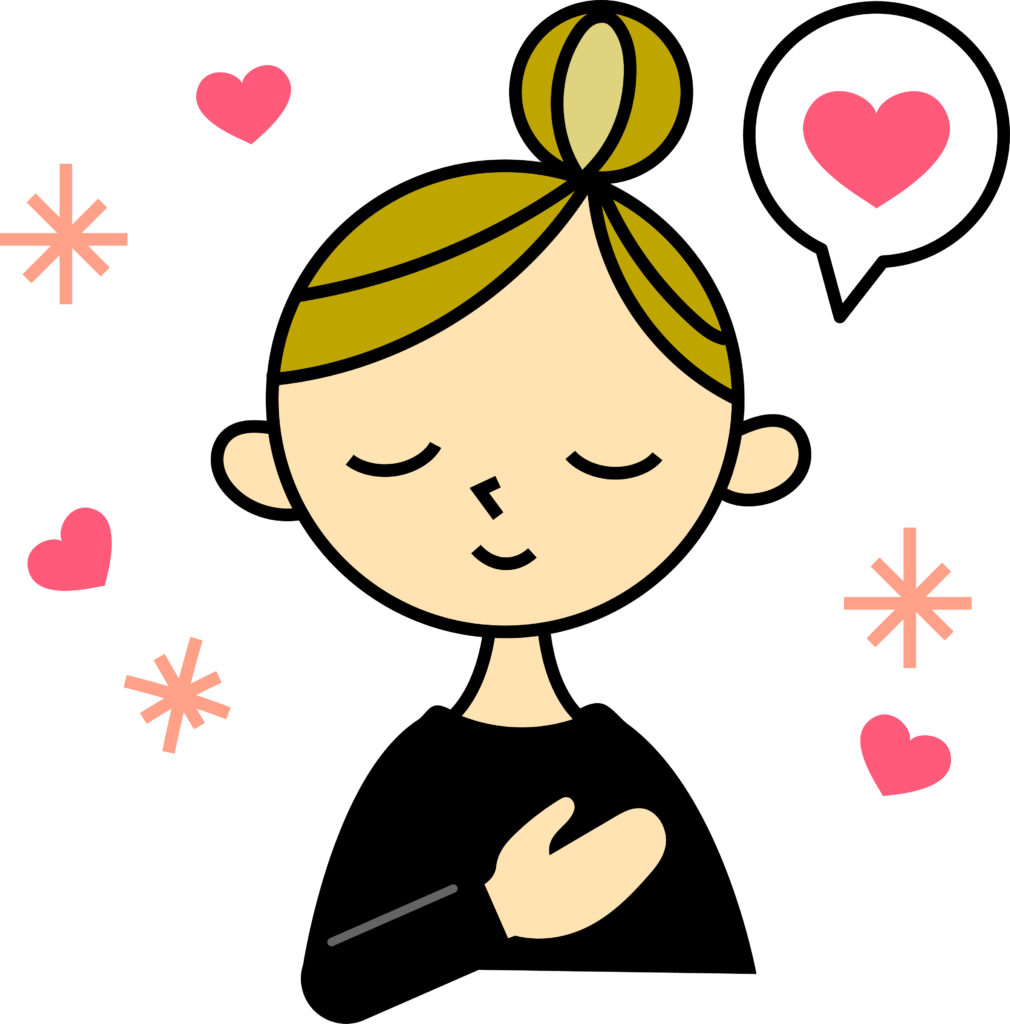
ここからは学校以外で実践できる悩みの減らし方をご紹介します。
こういった方法が取れない場合は、お気に入りのお散歩コースを探したり、ふらっと立ち寄れるお店を見つけておくのも良いでしょう。
“居場所”は単なる場所だけではありません。「この人といれば落ち着く」という人と定期的に会うのも、好きな曲を聴くのも、立派な居場所づくりです。
お散歩をして近所の人に挨拶するだけでも良いので、人と話してみましょう。他にも習い事に行ったり、コミュニティに所属してみたり、気になったイベントに参加したりするという方法もあります。
ネットで話す方がハードルが低くなるのであればオンラインのコミュニケーションでも良いので、何かしら話してみてください。
家族以外でも気兼ねなく話せる人を見つけることができたらベストです。
人と会うことが苦手な場合は、あえて完全に1人になるという方法を試すのも良いかもしれません。1人になることで落ち着くことができ、物事に取り組む気力が復活することもあります。
心身に関することが不登校の原因である場合に特に有効です。
忍耐力をつけることは確かに大事ですが、心が潰れてしまっては元も子もありません。それに、誰しも嫌なことばかりに取り組んでいては疲れてしまいます。生まれつき耐えられる量が少ない人だっています。
苦手な場所に行かない、苦手な情報は見ない、苦手なことはしない。これを徹底してみてください。少しずつ心が軽くなっていきます。
避けるのが不安な場合は、耐えられる程度に取り組んでみる、別のアプローチをしてみるなどの方法で解決できることがあります。勉強が苦手であれば、動画教材を見る、クイズ番組で学ぶ、遊びながら学べるゲームを使うといった方法を試してみるのも良いですね。
1人で考えているときは、ネガティブな思考に陥ってしまいがちです。周りの人と関わって別の視点を知ることで、1人では思い浮かばなかった考えが浮かびやすくなります。
まずは少し話を聞いてもらうだけ。ちょっと作業を手伝ってもらうだけ。ほんの少し一緒に動画を見るだけ。そのくらいのことでいいのです。周りの人に頼ってみてくださいね。作業を手伝ってもらうだけでなく、心の回復を手伝ってもらうのも「頼る」に含まれます。
ほとんどの人は、頼ってもらえると嬉しいものです。「迷惑をかけたくないから」と自分ひとりで解決する必要はありません。
頼ると簡単に言っても、実践するのはとても勇気のいることです。メールや手紙で伝えるようにすると、相談内容を書く → 伝えるという小さな2つのステップになるので、相談しやすくなります。試してみてくださいね。



口頭で伝えたい場合は、「そうだ、ちょっと話聞いて〜」などの軽めの話をする雰囲気で一歩を踏み出すと話しやすくなります。
まずは自分が自分の味方になってあげられているかを心に尋ねてみてください。味方の1人目を見つけられたら、少しずつ周りで味方になってくれる人を探していきましょう。
1人で悩んでいると落ち込みやすいので、意識的に他の人と関わる機会を増やしてみることが大切です。味方になってくれそうな人の候補は以下のようにたくさんいます。
相談相手を見つけられない場合は、新しい場所に飛び込んで多くの人と関わると良いかもしれません。他にも、心無い言葉に注意する必要はありますがネットの掲示板に書き込んでみるという方法もあります。いろいろな方向から探してみると見つかりやすくなります。
相談するのが苦手であれば、誰かに聞いてもらうことはせずにメモに書き出して言葉を整理するだけでも、少し心が軽くなります。
学校であれば生徒会長や校長、学校外では教育委員会や専門の相談機関など、悩みを解決してくれそうな人に聞いてみるのもひとつの手です。
心に深い傷を負っている場合は、カウンセラーに相談してみたり、精神科や心療内科を受診することも視野に入れてみてくださいね。
他にも、ネット上に同じような悩みを持っていて解決した人の話が載っていないか、調べてみるのも良いでしょう。


いろいろな考え方に触れてみたり、自分を肯定してくれる人と話したりすることで、今の自分を認めやすくなります。
好きなことや得意なことなどで、何か自分が役に立てるようなことをしてみましょう。家でお手伝いをしたら、家族に感謝してもらえるかもしれません。地域のコミュニティに入ったら、おじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれるかもしれません。SNSでコメントをしたら、やりとりしている相手の心を少し穏やかにできるかもしれません。まずは何か一つやってみるというだけでも効果があるので、ぜひ試してみてください。
得意なことを続けていると、「自分は上手くやれるんだ」と思えて気持ちが前向きになります。
自分の得意なことがわからないという場合は、どんなに小さなものでもいいので、周りから褒めてもらえるようなこと、自分が他の人よりも簡単にできるようなものがないか探してみましょう。
好きこそものの上手なれということわざがあるように、好きなことを継続することで得意になることもあります。



性格診断 (MBTI診断など) をして自分の特性を知ることでも、得意なことが見つかるかもしれません。
好きなことをすると、マイナスな気持ちに目を向けずに済み、エネルギーが少しずつ回復していきます。
好きなことすらできなくなっている場合は、休憩を多めに取るようにしてみてください。
好きなものがわからないという場合は、なんとなく惹かれるものを探してみてください。近所を散策して良いと思った風景を撮影したり、お店に行って目に留まった商品をメモしたり、いろんなゲームを試して面白いものを探したり… その中から共通点を見つけられたら、それが自分の好きなものである確率が高いでしょう。
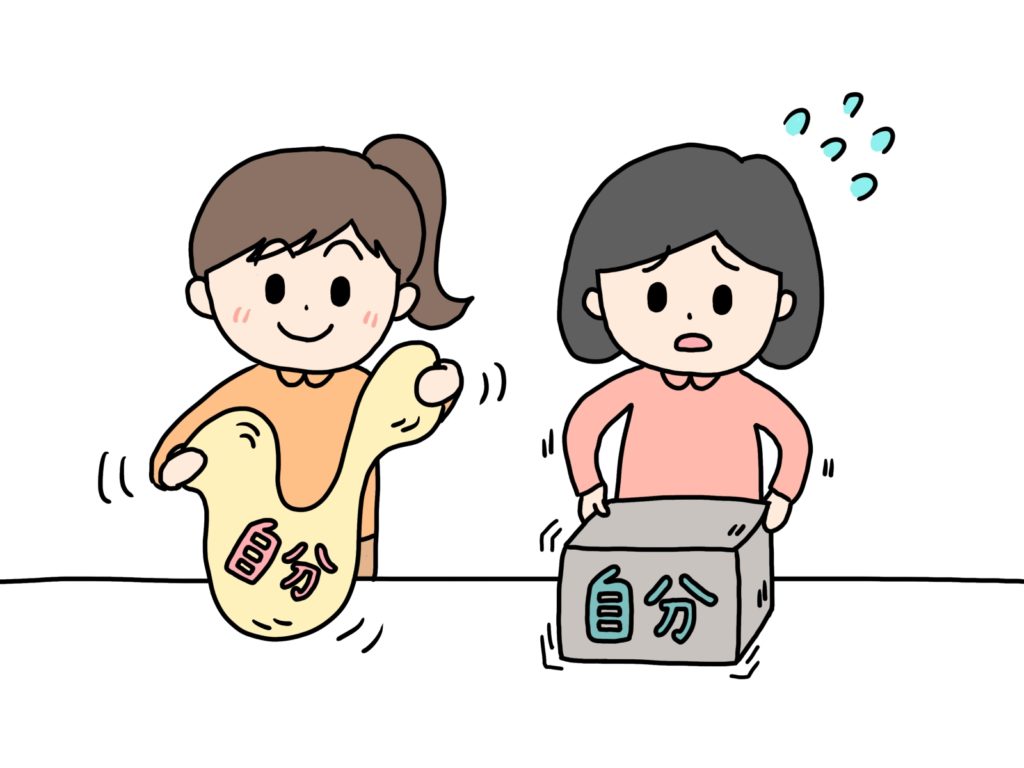
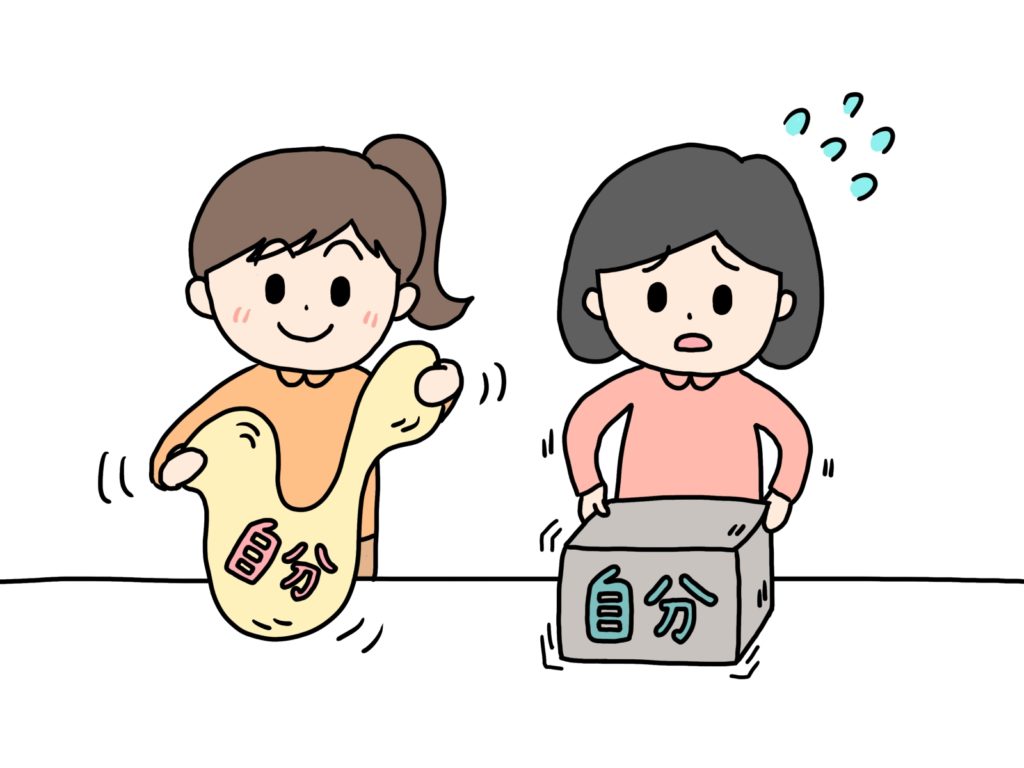
不登校の状態が続くと、物事をネガティブに捉えることが多くなってしまいます。考えている物事は、本当にネガティブな部分しかないのでしょうか?改めて別の視点から見てみましょう。
不登校の状態が続くことで、学校そのものが苦手になってしまうことがあります。そんなときは、自分が在籍している学校ではない、理想の学校を探してみましょう。
まずは自分なりの「理想の学校」を考えてみてください。私服登校ができる、パソコンを使って授業を行う、通うのは午後からでいいなど…。いくつか挙げられたら、条件に当てはまる学校を探してみてください。どうでしょう、少し学校のイメージが変わってきませんか?



学校に当てはまるものがない場合は、学校の代わりに居場所や学習できる環境を提供するフリースクール、主に家で学習を行うホームスクールといった、学校以外の場所で行われる教育にも目を向けてみてくださいね。
原因が何かというのは関係なくただ「苦手」という意識が先行してしまっている場合もあります。その場合は、「なぜ苦手なのか」を改めて考えてみましょう。
その後は少しずつ苦手を克服するのみです。学校であれば学校の前を通ってみるなど、少しずつ苦手なものに触れてみましょう。
この方法を試すことで苦しくなってしまう場合は、すぐに辞めて避けるようにしてくださいね。
勉強は学校の授業で扱うものだけではありません。ゲームが好きならプログラミングやゲームの歴史、デザインについて学んでみるというのも立派な勉強です。まずは好きなものを、好きなものがなければ身の回りのものを調べ尽くしてみましょう。
他にも、学校の勉強法が合わないだけという場合もあるので、様々な勉強法を片っ端から試してみるのも良いかもしれませんね。



私は周りに人がいると集中できないタイプなので、授業は聞いているフリをして家で勉強していました。
予測不能な将来を考える時はどうしても不安が付き纏うので、難しくはありますが今できることに目を向けるという方法が有効です。今できることの一例としては、好きなことや得意なことを続ける、資格を取るなどでスキルを磨いておくといったことですね。
いろいろな考え方やものに触れて視野を広げ、将来はいろいろな生き方があるとを認識するのも不安を取り除く一つの方法になります。
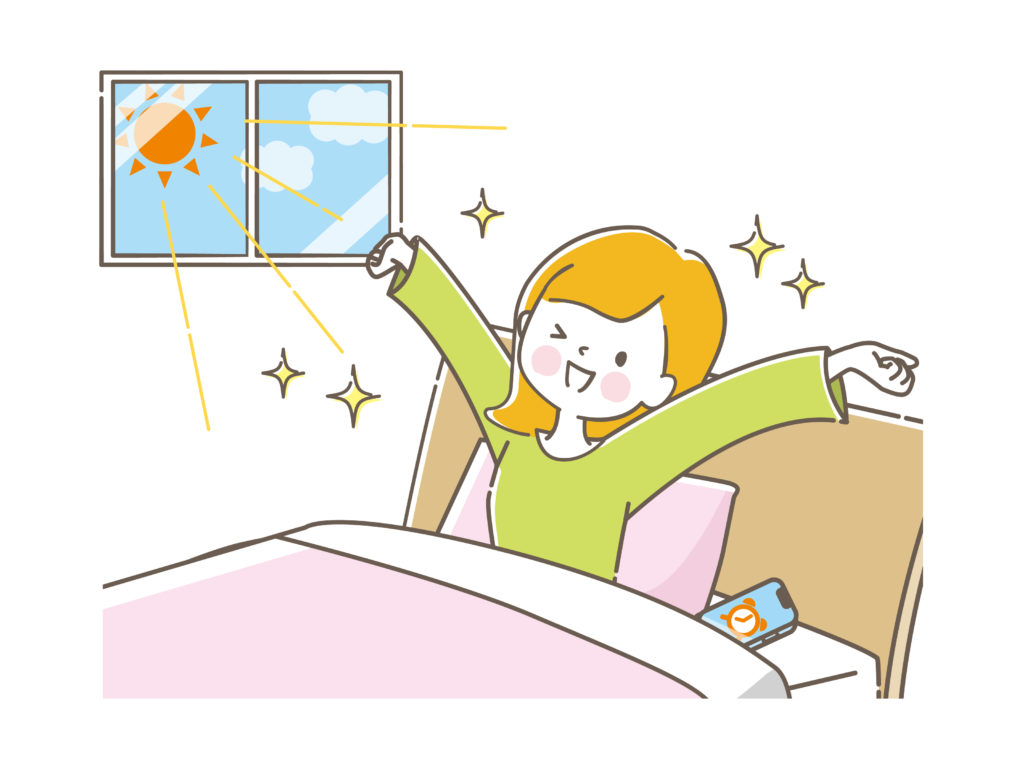
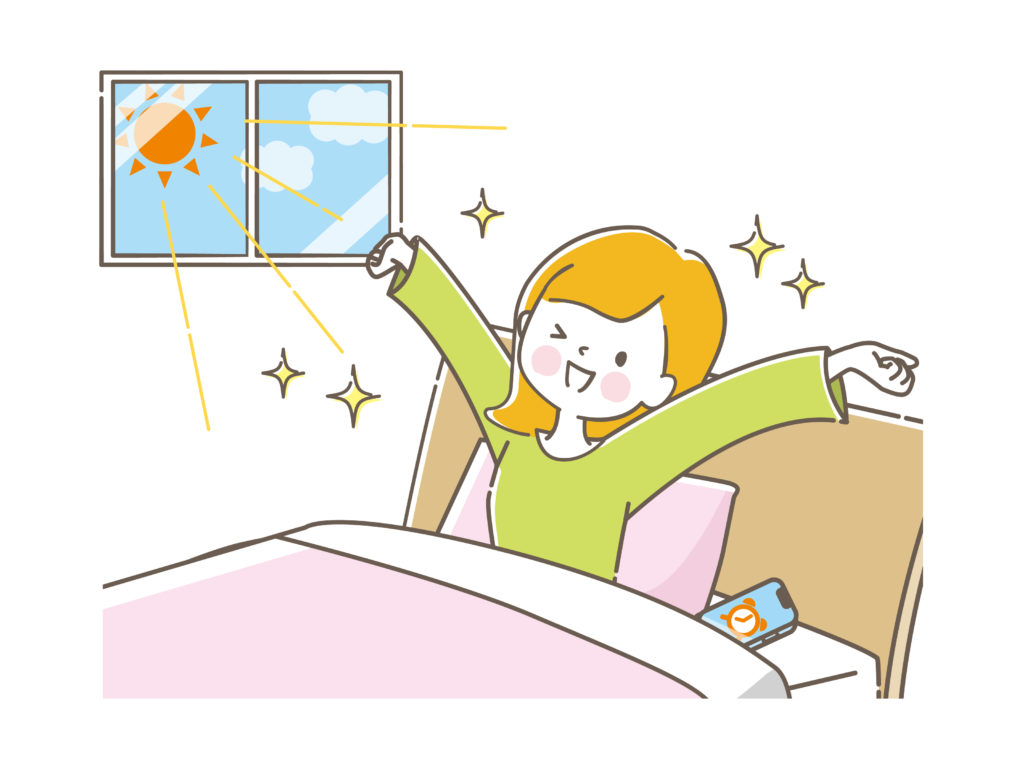
内側にある不安を解消するのと同時に、不安を増大させている外側の状況を改善するのも大切です。
いきなり生活リズムを変えると逆にストレスになってしまうので「眠くなったらお昼寝してもいいから、土日だけは10時までに起きる」など、達成できそうな緩い目標から始めてみると良いでしょう。
起きたら嫌なことが待っているという場合は無理にでも寝ようとしてしまうので、お昼から外出するなど楽しい予定を入れておくことで起きやすくなります。
ずっとゲームやインターネットをしていると、心だけでなく健康面などにも影響を及ぼします。かといって、ただやめるというのは難しいです。
他の物事にも目を向け、代わりとなる楽しい活動を見つけてみましょう。
他にも楽しいことがあると分かれば、自然と別のことに時間を使うようになっていきます。
学校には行かずに自分にとって有効だと思うことに時間を使う、前向きな「積極的不登校」に変わるという方法もあります。学校以外の場所でコミュニティに所属して活動する、やりたいことを極めるために時間を使うのも良いことです。



私は今、あえて登校せず将来のために時間を使うようにしています。そのおかげで、不登校であることによる苦しみや将来への不安は少しずつ和らいできました。


ここからは、実際に不登校の経験がある私がどのように不登校の原因を見つけられたのか、体験談を書きます。


私が初めて不登校になったのは、小学4年生の時です。クラスは学級崩壊寸前で、授業中は私語ばかりでまともに勉強なんてできません。先生はそんなクラスに対して毎日のように怒鳴っていました。時に教卓を凹ませるほど蹴り、時に問題のある生徒をベランダに無理やり引っ張り出しながら。
私は真面目すぎる性格もあって、そんなクラスで過ごさなければならないことがどうしても耐えられませんでした。当時学級委員長を務めており、子供ながらに「どうにかしなければ」という責任も感じていました。それでいくつか改善策を考えて実践したのですが、もちろん1人の生徒が学級崩壊寸前のクラスを変えられるはずもなく。格好の的になり散々当たられて終わりでした。
苦手な空間に1日中いなければいけないツラさと責任感から徐々に心は粉々になっていき、そのまま自分は学校へ足が向かなくなりました。
幸い親は「学校は無理して行かなくたっていい」「頑張って学校に行っていたんだから、今は好きなことをして過ごしてね」と言ってくれていました。それでも「学校は毎日通わなければいけない場所」という固定観念や「ちゃんと優等生でいなきゃ」「親に迷惑はかけられない」といった考えから学校に行けない自分を責め続け、好きなことをする余裕など一切ありませんでした。
周りの人が違う場所に行けばまた通えるようになると思ったので、中学は受験し奨学生として私立の中高一貫校に通い始めます。ごく普通の家庭で、私立に通うことを簡単に承諾してもらえるほどの金銭的余裕はなかったのですが、親は「また通えるようになってくれるなら」という思いで私立に通わせてくれたのでしょう。
しかしそれでも、1年生の頃から休みがちになってしまいました。2年生に上がるタイミングでは出席日数が足りず奨学生から外され、とうとう2年生の中盤で完全に行けなくなったのです。親に金銭的な負担と精神的な負担、2つの負担をかけてしまうことになり、また小学生の頃のように塞ぎ込むようになりました。


中学に上がって、苦手な環境から解放されたはずなのに。多少不満はあるものの、お昼にお弁当を一緒に食べるようなお友達が数人いて、授業をちゃんと受けることもでき、部活動にも楽しく取り組めていたはずなのに…。



理由がわからないぶん、小学生の頃より苦しみは何倍も大きいものでした。
このままでは将来どうなるかわからない、不登校を解決しなければという焦りから、不登校についての情報を集めるようになります。しかしインターネットに載っている情報を試しても、不登校支援の機関に相談しても、フリースクールに通っても、病院で診てもらっても、張り詰めた心が緩むことはありません。
そこからは理由を考えることに疲れ、動画を見て現実逃避をしながら過ごす日々が続きました。
しばらく経ったある日動画を見ていると、「繊細さん」という文字が目に留まります。これが不登校の理由を見つけられたきっかけになりました。動画を見て自分は繊細さん、HSPと呼ばれる性質を持っているのだとすぐに気づけるほどピッタリ当てはまったのです。
※HSP (繊細さん) = 感受性が強く、刺激に敏感な性質を持つ人を表す言葉
そこからHSPについて調べていくうちに、HSPには「人と一緒にいると疲れやすい」という特徴があることを知りました。私の場合この特徴が非常に強く、丸1日誰かと一緒にいたり、週3〜4回以上の頻度で人と会うことにより疲れてしまいます。これが私の、楽しいはずの学校にすら通えなくなった原因でした。


自分がHSPだということに気づいてからは、普通の生活をするためにも徹底的に苦手な環境を避けるようになりました。高校は登校の必要がない通信制高校を選びました。
しかし、何もしないままでは将来が不安ですし、これまで無駄にしてきた7年間、高校生にとっては人生の約半分という長すぎる時間を取り返さなければという思いが強く現れます。
そこで取り組み始めたのが課外活動でした。通信制高校で時間が多くあるのだから、将来働くために必要なスキルや経験を身につけようと思ったのがきっかけです。
自分は何が得意なのか、何が好きなのか、何をしたいのか、どう生きたいのか。それを見つけるための旅をしています。



青楓館の0期生としてこの記事を書いているのも、その活動のうちの一つです。
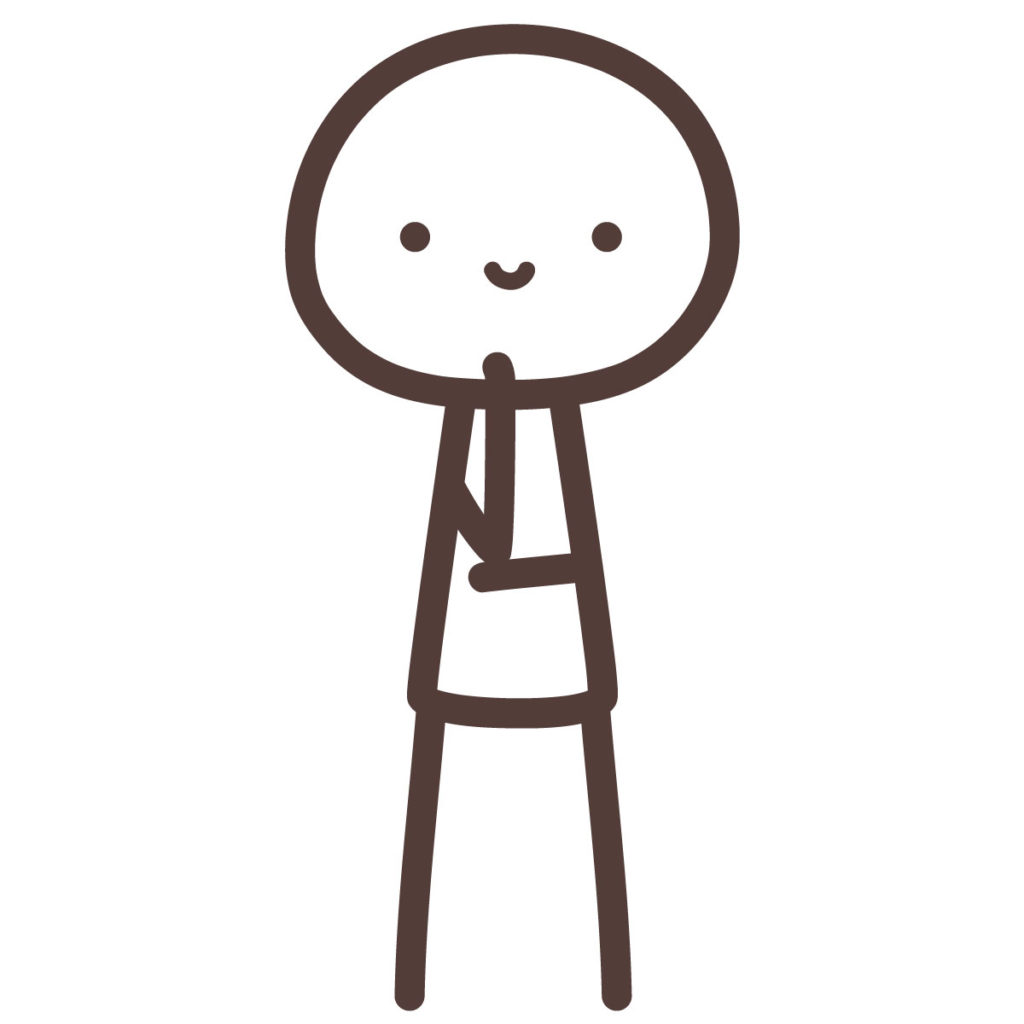
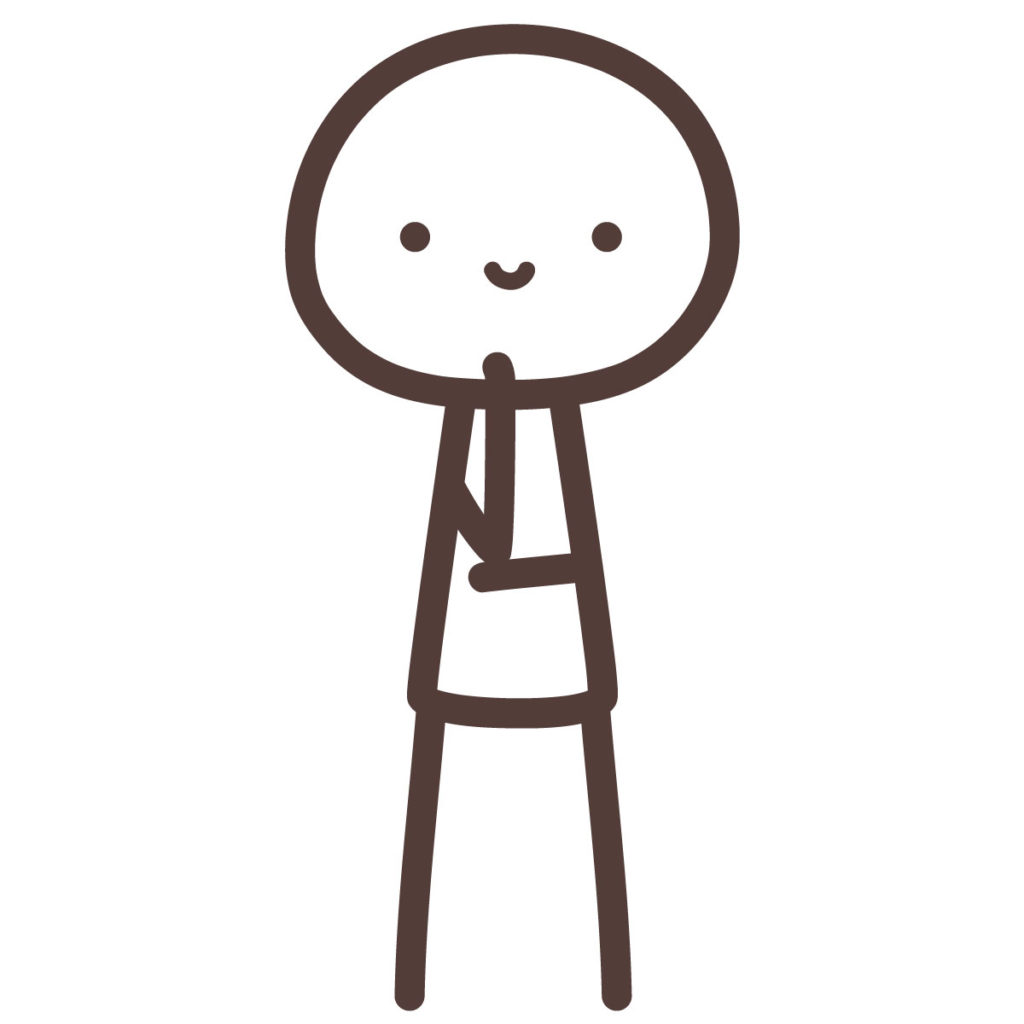
私は、なぜ不登校になったのか、それにどう対処するか、自分で納得のいく答えを見つけられるまで8年かかりました。大きな原因の後ろに小さな原因が隠れていたこと、小さな原因とそれへの対処法が当時は今ほど世間に浸透していなかったことから時間がかかってしまったのです。
それでも、8年かかってでも原因を見つけられた価値はありました。それは自分らしい生き方をしようと思えるようになったということです。いわゆる「普通」の生き方ができないのなら、ありのままの自分でいられる環境を徹底的に探さなければと思うようになりました。
課外活動を始めたことで、まだ抽象的ではありますが「自分らしい生き方」の答えに少しずつ近づいているような感覚があります。いつか「これが自分の生き方だ」と胸を張って言えるような生き方をすることが、今の私の夢です。


不登校による悩みは深刻で、改善するのはとても難しいです。自分のペースで少しずつ、エネルギーに余裕があるときに考えていきましょう。
それから最後に、自分は自分の味方でいてあげてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ライター:青楓館高等学院0期生 ユキハ
青楓館高等学院0期生として、メディア班で記事の執筆などを担当。
不登校の経験から自分らしい生き方を模索中。自分の好きな「言葉」を使って「HSPさんが生きやすい社会」を作るために活動しています。
コメント